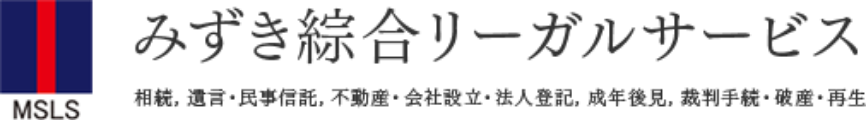民事信託(家族信託)
信託とは

「信託」というと、まず「信託銀行」が行う大きな財産の資産運用や、証券会社が行う株式などの有価証券の「投資信託」を思い浮かべるでしょう。「信託」の起源は中世ヨーロッパとも言われています。十字軍の遠征に参加する兵士たち(委託者)が、⻑期間領地を離れるにあたり、所有する財産の名義を信頼できる友人など(受託者)に預けて管理運用してもらい、そこから生じた収益を残った家族(受益者)に渡してもらったのです。
「信託」は、財産を管理したり、承継させたりするための制度のひとつです。ある人(「委託者」といいます)が、信頼するある人(「受託者」といいます)に自分の財産の名義を移転して、その人に責任を持って管理運用してもらい、そこから生ずる収益を自分の意図する人(「受益者」といいます)に給付してもらったり、最終的に承継させたりする制度です。
その中でも「民事信託」は、信託銀行が行う「商事信託」と異なり、「受託者」が営利を目的とせず、非営業で、継続反復して引き受けるのではないものをいいます。本来、私たちも利用することができ、身近なものであるはずなのですが、平成19年9月、85年ぶりに信託法が全面的に改正されて活用できるようになったものであるため、こうした法的サービスを提供できる法律専門職がまだまだ少なく、なじみがないのです。
民事信託(家族信託)で
できること
-

かゆいところに手が届く
「オーダーメイド」の財産管理・財産承継「民事信託」では、一般市民や中小企業が当事者となって、実現したい目的、ニーズに合わせてその仕組みをかなり自由自在に設計することができ、財産管理や承継に活用します。この「かなり自由自在」というのが、「民事信託」の最大のメリットです。
「民事信託」は、その人その人の事情にあわせた「オーダーメイド」の財産管理・承継方法を提供する法技術だと言えます。 -
民事信託を使うメリット
「民事信託」を使えば、成年後見制度を補完するような、配慮の行き届いた後見的な財産管理を行ったり、相続や遺言だけではとても実現できないような、将来を見据えた遺産承継を実現したりできます。
また、中小企業で「民事信託」を活用すれば、会社法の定款自治や種類株式の活用と組み合わせることにより、会社の経営者が不幸にして認知症になったり、急に死亡したりした場合の柔軟なリスクマネジメントとして役立てることができるのです。 -
「委託者」「受託者」「受益者」

信託には、委託者(財産を預ける人)、受託者(その財産を管理する人)、受益者(その財産から利益を受ける人)の3つの役割があります。
- 「委託者」
- 受益者の利益のため、受託者と信託契約を結びます。
- 「受託者」
- この信託契約に沿って、受益者のために、信託契約で決めた方法や順序で預かった財産を管理します。
- 「受益者」
- その財産から利益を受け取ります。
こんな方はご相談ください
-
親亡き後、障がい等をお持ちの
お子様のために
ご自身の判断能力が低下したときや、ご自身が亡くなった後のお子様の生活を支援するための信託です。
お子様が障がい等をお持ちで、ご自身が亡くなった際、その子が一度に財産を受け取ってもきちんと管理できるか不安がある場合等に対処できます。ご自身の判断能力が低下されたり、認知症になられたりした場合、ご自身による財産の管理が難しくなり、お子様の生活支援に支障をきたします。
また、ご自身が亡くなられた場合、生活支援が必要なお子様に定期的な財産支援や臨時の財産支援をするということが難しくなります。このような場合、信託を利用すれば、信託した財産について、今後の管理の方法やご自身が亡くなられた後の財産の管理の方法をあらかじめ決めておくことができます。
例えば「自分が亡くなった後は子供に現金を月に〇〇万円ずつ渡す」等決めておくことができ、お子様が将来にわたって安定した生活を送ることができます。 -
例えば、
次のようなしくみが考えられますポイント1 財産管理
特定障がい者のお子様を受益者として、将来にわたる生活の安定を図るために信託された財産を管理します。
ポイント2 信託財産
信託できる財産は、金銭・自宅・収益物件です。必要に応じて、組み合わせできます。
- 金銭…定期的給付のほか、実際の必要に応じた臨時の給付をします。
- 自宅…維持費等相当額以上の金銭を併せて信託しておきます。
※自宅と併せて信託する金銭は、自宅不動産維持費等のために使用します。もし、余剰額がでたら、生活費等として定期・臨時給付します。 - 収益不動産…維持管理等相当額を留保した上で、上がった収益を生活費等として定期・臨時給付します。
ポイント3 贈与税
贈与税が非課税となります。
- 特別障害者の方については6,000万円まで
- 特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで
(ただし、信託財産の処分等で収益が生じた場合は、受益者である特定障害者の方の所得となるため所得の種類に応じて所得税が課税されます。)
-
あとつぎへの遺贈

自分の死後は自宅の土地建物を妻(夫)へ、妻(夫)亡き後は子どもたちに土地建物を処分して現金にして渡したい。(あとつぎへの遺贈)
ご自身の遺言で配偶者に相続させた自宅土地建物などの財産を、配偶者の死後、さらにお子様に引きつがせることまでは、ご自身の遺言では確定できません。この信託では、ご自身の判断能力が低下した時・認知症になったときに備えての財産管理に加えて、万が一、ご自身が亡くなられたときに、まず第1段階として、残された配偶者には自宅の土地建物等を遺すとともに、安定した生活費を確保し、さらに第2段階として、配偶者が亡くなったときは自宅の土地建物を子供に引きつがせることができます。

自分の死後はまず、配偶者の安定した生活を確保したいし、さらに配偶者の死亡後は、お子様に円滑に財産を引き継げるよう備えておきたい方のための信託です。
また、家族の中に財産を預けておきたい適切な受任者がいない場合でも、福祉信託に特化した信託会社を受託者にしておくことで、お子様同士の相続争いを回避するよう、事前に準備しておくことができます。
-
おひとりさま

一人暮らしで生活には困らないけれど、兄弟とは疎遠にしている。
自分が万一の時に、葬儀や相続手続きはどうしたらいいのだろう?
兄弟たちに迷惑をかけたくない。
家族同様にかわいいペットも、自分のもしものことがあったらどうしたらよいだろう。これは、ご自身の亡くなった後の手続き等を決めておきたい方のための信託です。
葬儀や遺産整理、永代供養や遺贈・寄付などをご自身の希望する方法で滞りなく行うための資金を確保することができます。
近い親族や家族のいないお一人となった方、家族に迷惑をかけたくない、希望どおりの葬儀やお墓、遺品の整理などができるよう自分の亡き後のことをきちんとしておきたい、とお考えの方などに有効です。
家族同様に暮らしているペットも、ご自身に何かあったとき、誰かがかわって大切に世話をしてほしいとおもわれることでしょう。
自分の亡くなった後にやってほしい事を決めて、福祉信託に特化した信託会社を受託者にしておき、必要な資金を信託会社に預けておくことで親族の手を煩わせることなく決めたことを実現できます。
信託会社を預け先として資金を管理しますので、一般の個人や、親族などが受託者となったときに、その受託者が死亡したら?とか、受託者が使い込みをしたら?、などの心配がありません。
信託契約作成後の、
アフターフォローが
肝心です
-

家族信託では、受託者に一般の家族が就任するように信託契約を組成します。
このため、家族信託は契約の起案で終わるのではなく、実際に始まってみてから、個々の諸問題に対して、どのように対処すべきかを、サポートしていくことが必要となります。 -
信託登記を専門とするのは、
司法書士
通常、信託財産には不動産が含まれますから、信託財産の不動産には信託登記を行わなければなりません。このため、信託契約の趣旨を実現するために、登記の法律専門家である司法書士は、きわめて重要な役割を担うことになります。
信託の設定時には、信託目録をいかに作成するかが大切です。信託の終了時には、信託目録を更正するかなど専門的な知識が必要となります。