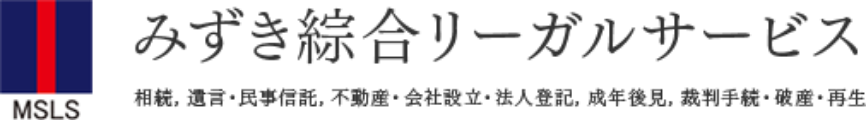不動産登記
不動産登記について

不動産を買おうとしたり、その不動産を担保に融資をしようとしたりする人達が安全に取引できるようにするために、不動産の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等とともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局備え付けの登記簿で公示するのが不動産登記の制度です。
登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。
さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。
不利益を被らないために、
登記は必要

表題部について変更がある場合、例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合に、登記をすることが義務付けられています。これに対して、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
しかし、買った不動産の所有権や、融資した貸金債権の担保に得た抵当権を誰に対しても主張できるようにするには、登記をしておかなければなりません(対抗力)。
登記をしないことによる不利益を回避するために、登記をしておくことが必要です。
登記手続きには、登録免許税という税金と司法書士の手数料(報酬)の2つが必要です。
登録免許税というのは、登記をするために必要な税金です。実際にご購入される時の税率と司法書士の手数料(報酬)については対象となる不動産の固定資産評価額によって段階的に決まっておりますので、お尋ねください。
不動産を売る時・買う時
-
不動産を売る時

不動産を売る場合、権利証、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)、固定資産の評価額を証する資料が必要です。
司法書士が作成する登記原因証明情報や委任状には、売主の実印が必要になります。
その他、農地を売買するときは事前に農業委員会の許可書、取締役が自分の会社との間で売買するときには利益相反のため株主総会または取締役会議事録が必要です。 -
不動産を買う時

不動産を買いたい場合には、先ず法務局で登記簿謄本を取得して、現在の登記上の所有者が誰になっているかを調べることが重要です。また、その不動産に差押や仮差押の登記、先順位の仮登記や抵当権等の登記がされていないか確認しなければなりません。これらの登記が残っていたら、せっかく自分の名義にしても、競売等により所有権を失うおそれがあります。
また、土地を購入された後に、希望する家が建てられるかどうかが問題になることがあります。
通常、不動産仲介業者が確認していますが、大きな買い物ですから、重要事項の説明を受ける際に、納得いくまでお尋ねになることをお勧めします。必要なら、当事務所の司法書士がアドバイスいたします。
その他、登記簿には、地目や面積、種類や構造、床面積等が記載されていますが、現況と一致していない場合もありますので注意が必要です。 -
マンションを買う場合
マンションの場合、区分された建物の専有部分と一緒に「敷地権」という土地の権利もいっしょに買うことになります。敷地権として、マンションの所有者全員で土地を共同所有することが一般的ですが、共同で土地を借りている場合もあります。
なお、中古マンションの場合、必ず確認していただきたいのが、前の所有者がマンションの管理費と修繕積立金を支払っているかどうかです。支払われていない場合、その未払い分をあなたが支払うことになりかねません。
家を新築したとき

家を新築したときは、第1に建物表題登記をすることになります。これにより、建物の物理的状況(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等)を公示します。ここまでは土地家屋調査士の仕事です。
次に、所有権保存登記を申請します。保存登記は、所有権の登記がされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。その後、建物の建築資金について住宅金融支援機構や銀行等から融資を受けた場合など、担保として抵当権設定登記がなされます。
家族に土地や建物を
贈与するとき

暦年贈与の場合、非課税となるのは年間110万円となりますが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産等を贈与した場合、その額が2,000万円(基礎控除額を合わせると2,110万円)までは、贈与税の配偶者控除を受けることができます。
また、相続開始前3年以内の贈与(令和6年以降に贈与される財産については、相続税の対象になる期間が順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与)については、相続税財産として持ち戻しの対象となりますが、この制度による贈与については持ち戻しの対象とはなりません。
ただし、贈与した年について贈与税の申告をお忘れなく。
また、相続時精算課税制度を選択する旨を税務署に届け出ると、60歳以上の親または祖父母から、推定相続人である18歳以上の子または孫への生前贈与について、累計2,500万円までの特別控除額の適用があり、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
しかし贈与者が亡くなったときは、この制度を使って贈与を受けた金額については、たとえ何年前の贈与であったとしても、相続財産に含めて相続税額を計算します。
その際、贈与時に支払った贈与税は、相続税から差し引くことになります。
なお、土地や建物の贈与を受けたときは、その名義を変更するための「贈与による所有権移転登記」が必要です。
贈与の場合の登録免許税率は原則として、土地建物の固定資産税評価額の2%となります。
令和6年1月1日以後に行う贈与については、相続時精算課税適用者が特定贈与者(親、祖父母)から受ける毎年110万円以下の贈与は申告不要となります。なお、上記2,500万円の非課税枠とは別枠となります。
110万円基礎控除(暦年課税の非課税枠)との選択適用のため、一度、相続時精算課税制度を選択すると、この制度を選択した贈与者の贈与については生涯この制度を適用することとなります。
税務監修:原田文香税理士事務所
住宅ローンを完済したとき
(抵当権抹消)

土地・建物の抵当権は、銀行等の貸金債権等を担保することを目的として登記されています。その債権は、住宅ローンの返済が終わったときに消滅し、抵当権は当然に消滅します。
しかし、登記簿上の抵当権は、当事者が抹消手続をしないと残ってしまい、そのままにしておくと不都合が生じてきます。特に抵当権者が金融機関などの法人でなく、個人の場合だとなおさらです。例えば、抹消手続きをしない間に登記簿上の抵当権者が死亡すると、抹消登記をするのに抵当権者の相続人全員の印鑑をもらわなければなりませんし、万一抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続きがより煩雑で手間のかかるものになってしまいます。また、新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主のために、結局は消滅した抵当権の抹消をしなくてはなりません。こうしたことから、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。費用もあまりかかりません。