会社設立・法人登記
会社設立・法人登記に
ついて
-

会社法では、個人で営業を始める場合でも会社形式にすることが簡単にできます。
会社形式にすれば、会社法の規定に則ってガバナンスしなければなりませんが、一度きちんと設計して設立すれば、事業の拡大や継続は個人の場合よりもやりやすくなります。当事務所では、設立の趣旨を丁寧にお伺いし、適切なアドバイスをいたします。
個人事業主の法人成りなのか、既存企業の子会社設立なのか、複合企業の合弁なのかによってご提案内容は当然異なります。さらに、仕事仲間との起業なのか、株主の人数、株主と役員とは重複するのか、スポンサーは別にいるかなどによって注意する点も異なりますので、細部にわたってご案内いたします。 -
どのような会社にするか?

おやりになりたいことを説明してくだされば、定款に記載する文言は、当事務所が最適の内容をご提案しますし、資本金と税金の関係、営業年度(=決算期)への配慮などもきちんとご説明いたしますので、ご安心ください。
会社法上の会社は、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)に分類されます。会社は相互に組織変更して種類を変えられます。一般的には株式会社の設立が多いのですが、コストがかからず、経営しやすい合同会社の設立もオススメです。あまり耳慣れませんが、皆さんもご存知のアップルジャパンや⻄友も合同会社です。
株式会社は不特定多数から資本を集めて経営を取締役に委ねます。経営の規模を拡大するのに向いており、その分責任ある経営が求められます。通常、最初は株式会社のうちの非公開会社の設立となるでしょう。株式の全部に譲渡制限がついた会社を非公開会社といい、株式を自由に譲渡できる公開会社とは態様が異なります。株式を自由に譲渡できず、株主全員が取締役になっている会社は、持分会社と似ているわけで、定款で自由に変更できる事項が多くなっています。
持分会社はいずれも社員の変更が少なく出資者全員が経営にあたることを予定しているので、経営自由度が高いのが特徴です。合名会社は社員全員が無限責任。合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在。合同会社は社員全員が有限責任社員であるため、株式会社に近い規定が適用されます。
会社の変更登記
-
株式

会社法では、多岐にわたる種類株式を発行できます。余剰金の配当、残余財産の分配、議決権の行使、譲渡制限、取得請求権、6取得条項、7全部取得条項、8拒否権、9取締役選任権について異なる種類の株式の発行が可能です。種類を組み合わせることによって、さらに多くの種類をつくることができます。これら種類株式は、業績向上や資金調達手段の充実を見据えて設計したり、少数株主の増加防止や第三者の経営参入排除などリスクマネジメントのために活用できます。なお、非公開会社の場合、株主個人ごとに余剰金の配当、残余財産の分配、議決権の行使を変えることもできます。
-
資本金

会社法では資本金額は株式数と関わりなく、株主総会決議によってのみ変更されます。ただし、取締役会に株式の発行を委任できるので、逐一株主総会の決議が必要なわけではありません。また、取締役会の決議のみで資本額を変更できる場合もあります。なお、資本額を減少する時は、株主総会決議の他に、債権者保護手続きを行わなければなりません。
-
役員変更

取締役及び会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までが原則です。ただし定款でそれより短い期間を定めることもできます。また非公開会社では10年まで伸ばすことができます。
監査役の任期は4年内に終了する事業年度の定時株主総会までです。それより短くすることはできませんが、非公開会社では10年まで伸ばすことができます。会計監査人の任期は1年ですが、解任決議をしない限り、自動継続です。選任決議は株主総会で行い、この総会の定足数を議決権の3分の1未満に減らすことはできません。代表取締役は取締役会や取締役の互選等で選任します。代表取締役自身の任期はありませんが、取締役の任期が切れれば代表取締役としての任期も終了します。有限会社の取締役及び監査役には任期がありません。 -
本店移転、支店設置
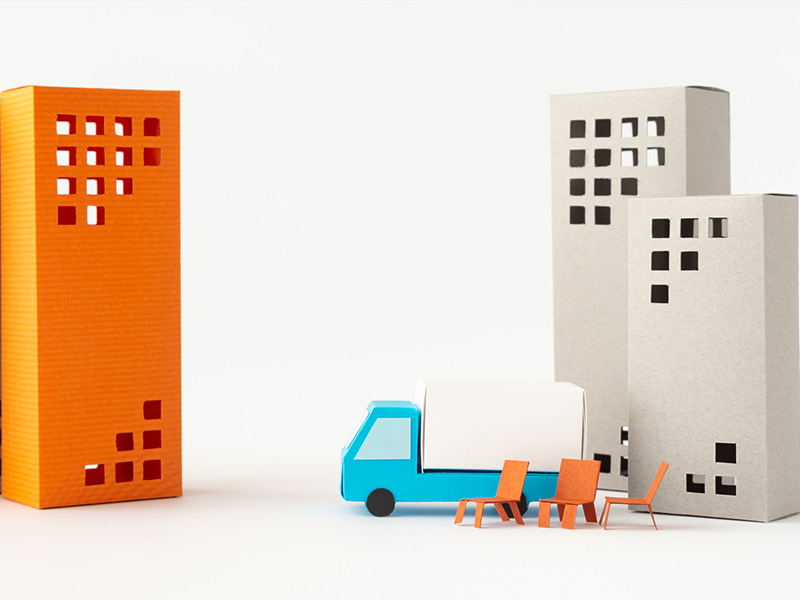
本店は会社にとっての住所。必ず1つで、2つ以上は置けません。本店を移転した場合は登記をしなければなりません。同じ登記所の管轄内で移転する場合の手続きは簡単ですが、従前の管轄から新しい管轄に移転する場合では登記の手続きが少し複雑です。
支店を設置した場合は、登記することができます。登記しなければその場所で営業できないわけではありませんが、支店での取引を円滑に行うためには、登記をすることをお勧めします。
また、支店に支配人を置く場合は、支店の登記が必要です。ただし支配人の登記は本店所在地で行います。支店を登記した場合、移転及び廃止する時にも登記が必要です。 -
企業再編の登記

企業再編には、合併、会社分割、株式交換、株式移転があります。この他、組織変更も企業再編の一種です。合併とは、2つ以上の会社が1つの会社に吸収されて他の会社が解散するか、あるいは2つ以上の会社が全て解散して新しい会社を設立することです。会社分割とは、1つ又は2つ以上の会社が事業の一部を分割して新しい会社を設立するか、他の会社に吸収させることです。(事業譲渡は会社分割に似ていますが、会社分割が包括的に権利義務を移転するのと違って、事業譲渡の場合は個々の権利義務を個別に移転しなければなりません。また、事業の全部を譲渡しても、譲渡会社は解散しません)
株式交換は、ある会社が別の会社の完全子会社となるため、子会社の株主全員が親会社と株式を交換します。親会社を新しく設立する場合は株式移転となります。組織変更は、持分会社が株式会社に、あるいは株式会社が持分会社に変更することです。
それぞれ株主総会決議と債権者保護手続きについて、細かな定めがあり、変更前の会社、変更後の会社について登記手続きが必要です。 -
有限会社の登記

会社法施行以来、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
一方、既存の有限会社は、「特例有限会社」といって、全て会社法上の株式会社であり、非公開会社として存続しています。
特例有限会社は非公開会社ですが、役員の任期、機関設計、株式の種類、株主総会の決議等、株式会社とは違う独自の規定が従来通り適用されています。
特例有限会社は商号変更することで株式会社になることができます。 -
解散・清算

事業をやめる時は解散登記が必要です。合併によって解散する場合以外は清算が始まり、清算結了することで法人格がなくなります。清算結了しないうちは会社の継続をすることができますが、⻑期間登記をしないでいると、みなし解散として登記簿が閉鎖されることがあります。
事業承継と⺠事信託の活用

会社の事業承継は大きな問題です。オーナー経営者に相続が発生すると、株式は特に指定をしなかった場合、法定相続人に相続されます。
同族会社の場合は、株式が相続人の間で分散されるため、会社経営が不安定になります。また、相続人が会社経営に参加していなかった場合でも、株主としての権利義務を負うことになります。
将来の事業承継を円滑に進めるための方策として、遺言や生前贈与で後継者に支配権を譲っておくことが考えられます。また、種類株式を活用して議決権の無い株式を発行することや、相続人に対する売渡請求権を定款で定める方法などもあります。
上記のような従来型の方策に加えて、最近注目を集めているのが⺠事信託の活用です。

会社の事業を、⺠事信託を活用して確実に有能な後継者に承継させたいという「事業承継のための信託」が増えています。
事業承継を考える場合には、株式によって表象されている、「経営権」と「財産権」の承継の2つを考慮する必要があります。
後継者が事業を継承していくうえで必要なのは、経営権です。
必ずしも会社の財産権を必要としているわけではありません。
ところが、自社株式をそのまま取得する場合、多額の税負担が発生します。
また、⺠法の相続法より、きょうだいの遺留分を侵害しない配慮も必要であるため、自社株式の多くを後継者が取得することは難しくなります。

信託を活用すると、財産権すなわち受益権は後継者以外の相続人も入れて遺産分割をし、ただし経営権に必要な議決権は後継者が保持するようなことが可能になります。
しかし、信託制度を利用する時に、税に関することも十分に意識をして進める必要があります。事業承継による信託を利用すると、事業承継税制の特例措置(事業承継による相続税・贈与税の納税猶予、免除の特例)の利用ができなくなります。
このため、信託により財産を移転する場合と、通常の贈与・相続により財産を移転する場合とで、税制からみてどちらが低コストで有利なのか、どの制度をどのように利用したらよいのか理解をしたうえで、選択をしていかなければなりません。
このような方は
ご相談ください
-
事業用財産及び株式等が相続で分割され分散してしまうのを回避したい

企業の経営者、オーナー経営者、または個人事業主とその親族の方々が信託の活用当事者となります。多くは非上場の会社がその事業用財産及び株式等の承継を計画されますが、個人事業主の場合も同様で、その事業の基盤になっている個人所有の不動産や重要な動産等を信託財産とします。
この信託は、第一に会社の株式の相続等による分散を防止して、⻑期にわたり安定した会社経営の基盤をつくることを目的としています。
事業用財産及び株式等が確実に後継者に引き継がれ、事業が継続・安定して行われることを実現させるためのものといえます。
最も大切なのが、「株式」の扱いであることは言うまでもありません。例えば、次のようなパターンが考えられます参考までに一例をあげるなら、次のようなパターンが考えられます。
いずれも内容は難しく、複雑です。事業承継の信託はケースバイケースで、状況に応じて、最も適した工夫をしなければなりません。パターン1 オーナー経営者が高齢のケース
オーナー経営者が高齢になり、全ての財産の管理等ができなくなったため、信託を組成して、後継者や設立した受託者法人に株式や事業用不動産等を移転しその管理運用等を委託します。この場合、全ての財産・権限を委託するのではありません。
- 株式の議決権についてはオーナー経営者が留保し、自らまたは自らが定めた指図権者が議決権を行使します。
- これにより役員等の地位を確保して、役員報酬・配当金等の受取を確実します。
パターン2 直系卑属の後継者が未確定のケース
経営者の直系卑属の後継候補者が未成年であったり、他社に勤務していたりして、後継者が確定していない場合や、経営者の直系卑属がなく、親族や特定の関係者から選任する必要がある場合に、親族や共同経営者あるいは設立した受託者法人に株式や事業用不動産等を移転しその管理運用等を委託します。
パターン3 後に直系卑属の後継者へ事業を引き継がせるケース
経営者の遺言により信託を定め、親族や共同経営者あるいは設立した受託者法人を受託者として株式や事業用不動産等を移転しその管理運用等を委託、当初受益者を経営者の配偶者に、後継受益者を本命の直系卑属の後継者に定め、信託期間の経過後、合意による信託の終了によって事業を帰属権利者たる直系卑属の後継者に引きつがせます。

